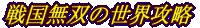 戻る 戻る |
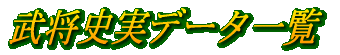 |
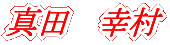 さなだ ゆきむら さなだ ゆきむら |
大坂冬の陣・夏の陣にて、豊臣方の武将として活躍した。大坂城の出城・真田丸を作り、攻め手の徳川勢を苦しめた。
徳川家康が一番恐れた戦国武将・真田昌幸を父に持ち、その父から受け継いだ巧みな軍略を発揮した。大坂夏の陣では、徳川家康をあと一歩というところまで追いつめたが、多勢に無勢のため、家康を討ち取ることはできなかった。
戦場にて、力尽き、徳川勢に討たれた。 |
|
|
 まえだ けいじ まえだ けいじ |
織田信長に仕えた前田利家の一族の出だったが、主君に仕えることはなく、無法者として、”かぶく”ことで周囲の人々を驚かせていた。
剣術の腕前は確かなものだったことから、あの豊臣秀吉が召し抱えようとしたが、自分が気に入らぬ主君には仕えるつもりはないとして、秀吉の誘いを断った。
結局、越後の上杉謙信の跡を継いだ上杉景勝に仕え、関ヶ原の役では、東軍の奥州勢相手に活躍した。 |
|
|
 おだ のぶなが おだ のぶなが |
”天下布武”の名の下に、天下統一の野望を燃やした戦国最強の風雲児。
羽柴秀吉や明智光秀など有能な人物を重く用いて、勢力を一挙に拡大させ、あと一歩というところまで天下統一制覇を進めた。
しかし、京都の本能寺にて、油断したところを重臣の明智光秀に襲撃され、獅子奮闘の力戦をしたが、抗戦むなしく、無念にも自刃して果てた。 |
|
|
 あけち みつひで あけち みつひで |
美濃の名族・土岐氏の流れを持つ名門生まれだったが、戦乱で一族が没落していたため、光秀は諸国を流浪した。
越前の朝倉氏に仕えていたが、そこに避難してきていた足利義昭に見いだされ、これに仕えた。織田信長が勢力を拡大させたとの話を伝え聞いた光秀は、足利義昭を織田信長へ会わせる折衝役を務め、これを見事、成功させた。
その後、光秀は織田信長にも仕えるようになり、徐々に頭角を現し、いつしか織田家重臣へと上り詰めた。織田家中で光秀がもっとも出世を競ったのが、羽柴秀吉であった。
織田家重臣として、活躍を見せていた光秀であったが、丹波国攻略に10年を費やしてしまい、徐々に活躍にかげりが見え始めた。信長が活躍しない重臣を次々と追放する処断に出たことで光秀は焦ることとなる。
また、光秀は足利幕府の重鎮だった土岐氏一族の生まれだったため、信長のように旧体制や旧権力を次々と廃止したり、軽んじたりする考えややり方に同調することができなかった。
光秀が織田信長に対して、謀反を起こす決定的原因となったとされているのが、10年かけて、光秀が平定し、領有していた丹波国を全て、信長が取り上げてしまったこと。光秀には代わりに出雲・因幡の二カ国を与えるとしたが、その国はまだ敵・毛利氏の領地だったことから、実質的に光秀とその家臣たちは、ともに我が家を失ったも同然だった。
ここにきて、光秀は、ついに信長への不満を爆発させ、本能寺に手勢で泊まっている信長を1万3千の軍勢で奇襲したのだった。戦国時代でもっとも日本が激震した”本能寺の変”が起こり、絶対権力者だった織田信長は無念な最期を遂げた。
光秀は、京都、近江を抑え、織田信長に代わって、天下人となったが、それも束の間であった。中国攻めの最中だった羽柴秀吉が、”本能寺の変”の報せを受け、すぐさま全軍を姫路城まで撤退させたのだった。
疾風迅雷の早さで姫路城まで撤退した秀吉は、城にあった金銀財宝を全て、兵士たちに分け与え、明智光秀打倒で決起した。
秀吉の素早い引き返しに、光秀は満足な準備もできずに”山崎の戦い”にて、秀吉軍に大敗し、山崎山中へと落ち延びていった。しかし、土民の”落ち武者狩り”に遭遇した光秀は、あえなく討たれてしまった。信長を討って、わずか13日間の短い天下人だった。 |
|
|
 いしかわ ごえもん いしかわ ごえもん |
| 豊臣秀吉が天下統一を成し遂げた後に、世間を騒がせた大盗賊の頭。京都や大坂などへ出没し、盗賊行為を行っていたが、秀吉の命令で捕まり、大釜でゆで殺された。 |
|
|
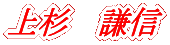 うえすぎ けんしん うえすぎ けんしん |
北陸屈指の名将。”軍神”と諸将に呼ばれ、恐れられた。天才的な軍略を見せた。北陸・信州・関東と各地を転戦し、武田信玄、北条氏康、織田信長と激しく戦った。
旧体制の室町幕府などに強い関心を持ち、世の中に秩序を取り戻すべく、義戦を展開した。
あの武田信玄と五度にわたって戦い合った”川中島の戦い”は、戦国史の中でもあまりにも有名な決戦の一つとなっている。 |
|
|
 おいち おいち |
織田信長の実妹。絶世の美女と謳われ、政略結婚のため、近江の浅井長政に嫁いだ。一男三女を産み、夫・長政とともに仲むつまじく暮らしたが、実兄・信長の天下野望に対し、夫・長政が反発。
”姉川の戦い”など浅井氏と織田氏は、激しい勢力争いを繰り広げた。三年あまりにも及ぶ激戦で、浅井氏は織田氏に敗れ、滅亡するとお市は、織田信長の下へ引き渡された。
お市と三女は助命されたものの、長男の万福丸(まんぷくまる)は、浅井氏の跡取りという地位にあるため、わずか5歳ほどで斬首となってしまった。
その後、お市は織田家重臣の柴田勝家へと再婚を果たし、越前北ノ庄にて幸せに暮らしたが、それも束の間であった。兄・信長が”本能寺の変”に倒れると政局は激震し、明智光秀を打ち破って、主君の仇を取った羽柴秀吉が織田家中で権力を独占。
秀吉と対抗する柴田勝家は、”賤ヶ岳の戦い”にて秀吉と激突したが、軍略に勝る秀吉にかなわず、あえなく大敗。
越前北ノ庄にて、迫り来る秀吉軍の侵攻になすすべなく、お市は、夫・勝家とともに自害して果てた。
お市の忘れ形見となった実娘の三女たちは、みな秀吉に保護され、長女・茶々は秀吉の側室となり、後に豊臣家の跡取りとなった豊臣秀頼を生んでいる。
次女のお初は、名門・京極高次の正室となった。
三女のお江は、徳川家康の跡取り息子・徳川秀忠の正室となり、後に徳川幕府三代目将軍・徳川家光を生んでいる。
お市の血脈は、名門の家柄へと確実に受け継がれていったことになる。 |
|
|
 おくに おくに |
| 戦国時代に華咲いた歌舞伎芸能の祖といわれている人物。出雲の巫女が踊りの名手として、評判をはせるようになり、それを見せ物として興行するようになった。後に後陽成天皇の女御近衛氏のために踊りを演じたと伝えられている。 |
|
|
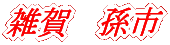 さいか まごいち さいか まごいち |
紀伊和歌山の生まれ。一向一揆勢に加わり、織田信長に拮抗した。鉄砲の名手として知られ、幾度となく織田信長の命をねらい、狙撃を試みている。
信長狙撃で、信長の太ももを打ち抜いたと伝えられている。 |
|
|
 たけだ しんげん たけだ しんげん |
戦国最強の騎馬軍団を作り上げた。また、すぐれた軍略を駆使して、領土拡大を進め、甲信地方の制覇とともに、東海道へと勢力を広げていった。
宿敵・上杉謙信との五度に渡る川中島の戦いを経て、信玄は京都へと攻め上がる野望を見せ、織田・徳川連合を攻め破っていった。
しかし、京都へと攻め上る時期が遅すぎたのか、無敵を誇る武田軍も信玄が病没したことで、次第に落ち目となっていった。信玄の跡目を継いだ武田勝頼は、長篠の戦いに大敗し、その後も外交の失敗で、孤立化を進めてしまい、名門・甲斐武田家は滅亡するに至る。 |
|
|
 だて まさむね だて まさむね |
”独眼竜(どくがんりゅう)”の異名を取り、若武者ながら、豊臣秀吉、徳川家康と並み居る歴戦の諸将と対等に拮抗するすぐれた外交能力を持った。
若干18歳で奥州名門・伊達家の家督を継ぎ、わずか24歳で奥州の覇者とまで言われるほどの領地拡大を成功させた。関東の北条氏と手を結び、豊臣秀吉に拮抗する動きを見せたが、秀吉が北条氏の小田原攻めを敢行すると、政宗はかなわないと悟り、白装束を着て、秀吉に降伏。
その後は、秀吉お気に入りの大名の一人となって、うまく外交を立ち回った。
秀吉没後は、いちはやく徳川家康と政略結婚を進め、徳川氏との結束を固めた。関ヶ原の役では、奥州の抑えとして会津の上杉景勝と交戦。
大坂の役では、伊達軍の騎馬鉄砲隊が大活躍した。大坂の役後は、天下のご意見番として、徳川幕府の頼れるシンクタンクとなった。 |
|
|
 のうひめ のうひめ |
| ”マムシ入道”と呼ばれ、諸将から恐れられた斎藤道三の愛娘。”大うつけ”と呼ばれていた尾張の無法者・織田信長へと嫁いだ。信長との間には、子は恵まれなかった。 |
|
|
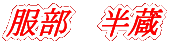 はっとり はんぞう はっとり はんぞう |
伊賀忍者を扱い、徳川家康に仕えた。1582年本能寺の変が起きた時、家康は京都にいたため、命をねらわれることとなった。その時、伊賀越えを敢行した家康を助け続けたのが、服部半蔵だった。
後に家康が江戸城を築城した際に、半蔵に逃げ道となる門を護らせ、その門は半蔵門と呼ばれるようになった。 |
|
|
 もり らんまる もり らんまる |
| 森可成の子。森長可の弟。織田信長の小姓として仕えた。まれにみる美男子と伝えられる。本能寺の変では、織田信長の側近として、明智軍と戦った。信長自害後、蘭丸は弟・力丸、坊丸とともに明智軍と戦い討ち死にした。 |
|
|
 はしば ひでよし はしば ひでよし |
尾張中村の農民の子。
今川義元の家臣・松下加兵衛に仕え、後に尾張の織田信長に仕えた。草履取りから台所奉行へと出世し、次々と功労を上げ、ついには織田家重臣にまで上り詰めた。
秀吉の上げた功労の中でも目を見張るのは、わずかいち夜にして、美濃国に墨俣城を築いたこと。現在で言うところのプレハブ工法を駆使して、短時間のうちに築城を成し遂げた。
その後、近江国に領地をもらい、織田家中でも出世頭として活躍し続け、織田信長の命を受け、中国地方攻めの総大将を任されるまでになる。
本能寺で主君・信長が無念な最期を遂げると、秀吉は”中国大返し”を行い、わずかな日数で近畿へと舞い戻り、謀反人・明智光秀と対戦。
みごと、光秀を打ち破り、織田家の実権を握ることに成功した。その後は、同僚だった滝川一益や柴田勝家を討ち滅ぼし、豊臣政権を樹立。
日本各地を転戦し、1590年には、ついに天下統一を成し遂げた。
その後、朝鮮出兵などを行い、政策の失態を行ってしまい、豊臣政権の崩壊を招くこととなった。秀吉没後、関ヶ原の戦いを境として、豊臣家の没落が始まり、大坂の役にて、豊臣家は滅亡するに至った。 |
|
|
 いまがわ よしもと いまがわ よしもと |
今川家当主として、君臨。”東海道一の弓取り”と称され、天下人となる野望を持つ。甲斐の武田信玄、相模の北条氏康と政略同盟を結び、甲相駿三国同盟(こうそんすんさんごくどうめい)と呼ばれた。
三河の松平広忠を屈服させ、尾張の織田信秀と対抗していた義元だったが、信秀が病没し、その跡目を継いだのが”大うつけ”と噂された信長だったことから、上洛の好機と見て、尾張侵攻を開始した。
しかし、信長の巧みな戦術のため、義元がいる本陣の場所を突き止められてしまい、信長率いる2000の突撃隊に奇襲されてしまう。義元は自ら大刀を振るって応戦したが、かなわず、討たれた。 |
|
|
 ほんだ ただかつ ほんだ ただかつ |
徳川四天王の一人。”家康にすぎたるものが二つあり。唐の頭に本多平八郎”と謳われた猛将。名槍”トンボ斬り”を使い、数々の戦場で軍功を上げた。
忠勝の娘は、あの真田昌幸の長男・真田信幸へと嫁いでいる。そのため、真田昌幸・幸村は西軍につき、信幸は東軍についた。ちなみに幸村の妻は、関ヶ原の役で西軍についた大谷吉継の娘。
関ヶ原の役では、徳川家康の本陣のすぐ前に手勢800を率いて布陣した。合戦終盤に島津義弘率いる軍勢が正面退却を開始すると忠勝は手勢を率いてこれを追撃した。しかし、島津軍のしんがりを務める鉄砲隊に馬を撃ち抜かれ、忠勝は落馬してしまった。 |
|
|
|
|